うるぷろでは、中小企業診断士などの国家資格保有者を多数パートナーとしています。中小企業診断士の仕事内容の一つとして、補助金の申請や銀行からの借り入れ時に必ず必要となる、事業計画書の作成を支援することがあります。事業計画書の作成には、その事業を取り巻く外部環境、内部環境を調査、分析し、事業を成長に導くための事業戦略を検討します。それら分析には多数の戦略フレームワークを使用します。その代表的な一つが「3C分析」です。3C分析は、事業戦略の中のマーケティング戦略を立案する上で非常に重要なフレームワークです。本記事では、3C分析の目的、手順、注意点に加え、4C分析や6C分析との違いについてもわかりやすく解説します。

3C分析とは?基本と重要性
3C分析の定義と構成要素
3C分析は、元マッキンゼー・アンド・カンパニーに所属していた経営コンサルタントである、大前研一氏により提唱されたフレームワークです。3C分析は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素を分析し、事業の成功要因を導き出すフレームワークです。それぞれの要素を深く理解することで、効果的なマーケティング戦略の立案に繋げることができます。
3C分析は、単なる現状分析に留まらず、将来の市場動向や競合の動きを予測し、それらに対応するための戦略を練る上でも非常に有効です。特に、変化の激しい現代のビジネス環境においては、常に最新の情報に基づいた3C分析を行い、戦略を柔軟に修正していくことが求められます。
また、3C分析の結果は、企業全体の戦略だけでなく、個々の部門やプロジェクトの戦略立案にも活用できます。例えば、新製品の開発においては、顧客ニーズ、競合製品の状況、自社の技術力を考慮することで、市場競争力の高い製品を開発することができます。
3C分析を行う目的
3C分析の主な目的は、市場の機会と脅威を把握し、自社の強みと弱みを明確にすることです。これにより、競争優位性を確立し、持続的な成長を可能にする戦略を策定できます。
具体的には、3C分析を通じて、どの顧客層をターゲットにすべきか、競合他社に対してどのような差別化を図るべきか、自社のどのような強みを活かすべきか、といった重要な意思決定を行うための基礎情報を得ることができます。これらの情報は、マーケティング戦略、製品開発戦略、営業戦略など、様々な戦略の策定に役立ちます。
さらに、3C分析は、リスクマネジメントにも貢献します。市場の脅威を早期に発見し、それに対する対策を講じることで、事業の安定性を高めることができます。また、自社の弱みを認識し、改善策を講じることで、競争力を強化することができます。
3C分析のメリット・デメリット
3C分析は、市場環境の全体像を把握しやすく、戦略立案の基礎となる情報を得られるというメリットがあります。一方で、情報収集に時間がかかる場合や、主観的な判断が入りやすいというデメリットも存在します。
メリットとしては、まず、3つの視点から多角的に分析することで、市場の全体像を把握しやすくなります。これにより、自社の立ち位置を客観的に評価し、取るべき戦略を明確にすることができます。また、3C分析は、戦略立案に必要な情報を体系的に整理し、提供するため、効率的な戦略立案を支援します。
一方デメリットとしては、情報収集に手間と時間がかかる点が挙げられます。特に、競合他社の情報や市場動向に関する情報は、容易に入手できない場合もあります。また、分析者の主観的な判断が入りやすいという点も注意が必要です。客観的なデータに基づいて分析を行うように心がける必要があります。
これらのデメリットを克服するためには、信頼性の高い情報源を活用し、複数の担当者で分析結果を検証することが重要です。
3C分析の具体的な手順

顧客(Customer)分析
顧客分析では、市場規模、顧客ニーズ、購買行動などを調査します。PEST分析やファイブフォース分析などのフレームワークを活用しながらマクロ・ミクロ環境を詳細に分析することが重要です。
市場規模を把握するためには、過去のデータや統計情報を収集し、将来の成長予測を行うことが有効です。顧客ニーズを把握するためには、アンケート調査、インタビュー調査、顧客データ分析など、様々な手法を組み合わせることが重要です。購買行動を把握するためには、顧客の購買履歴、Webサイトのアクセスログ、SNSの投稿などを分析することが有効です。
PEST分析とは、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの視点から、マクロ環境を分析するフレームワークです。ファイブフォース分析とは、新規参入の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、代替品の脅威、業界内の競争の5つの力関係から、ミクロ環境を分析するフレームワークです。これらのフレームワークを活用することで、より詳細な顧客分析を行うことができます。
競合(Competitor)分析
競合分析では、競合企業のシェア、戦略、強み・弱みを分析します。競合他社の動向を把握することで、自社の差別化戦略を明確にすることができます。
競合企業のシェアを把握するためには、市場調査データや業界レポートなどを活用することが有効です。競合企業の戦略を把握するためには、競合企業のWebサイト、IR資料、ニュースリリースなどを分析することが有効です。競合企業の強み・弱みを把握するためには、SWOT分析などのフレームワークを活用することが有効です。
競合分析を行う際には、単に競合企業の情報を収集するだけでなく、その情報に基づいて自社がどのように差別化できるかを検討することが重要です。例えば、競合企業が提供していないサービスを提供したり、競合企業よりも高品質な製品を開発したりすることで、競争優位性を確立することができます。
自社(Company)分析
自社分析では、自社の経営資源、技術力、ブランド力などを分析します。SWOT分析などのフレームワークを活用し、自社の強み・弱みを客観的に評価することが重要です。
経営資源を分析する際には、人材、資金、設備、知的財産など、自社が保有する資源を網羅的に評価することが重要です。技術力を分析する際には、特許取得状況、研究開発投資額、技術者のスキルなどを評価することが重要です。ブランド力を分析する際には、顧客認知度、顧客ロイヤリティ、ブランドイメージなどを評価することが重要です。
SWOT分析とは、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つの視点から、自社の内部環境と外部環境を分析するフレームワークです。SWOT分析を活用することで、自社の強みを活かし、弱みを克服し、機会を最大限に活用し、脅威を最小限に抑えるための戦略を策定することができます。
3C分析を成功させるためのポイント

3C分析を行う際の順序
3C分析を実施する際には、顧客、競合、自社の順で実施することを推奨します。理由は、第一に顧客を分析することで、対象事業の市場環境を体系的に理解し、次に、その市場環境に対し競合は何をどのように提供しているのかを分析します。そして最後に自社を分析することで、競合との差別化要因が何かを明らかにすることができ、重要成功要因(KSF)を明確に定めることができます。
客観的なデータに基づいた分析
3C分析を行う際は、主観的な意見や憶測を避け、客観的なデータに基づいて分析することが重要です。市場調査データや顧客アンケートの結果などを活用しましょう。
客観的なデータに基づいて分析を行うためには、まず、信頼性の高い情報源を選択することが重要です。例えば、政府機関が発表する統計データや、専門調査機関が実施する市場調査データなどは、信頼性が高い情報源と言えます。また、顧客アンケートを実施する際には、回答者の偏りを防ぐために、無作為抽出法を用いることが重要です。
さらに、収集したデータを分析する際には、統計的な手法を用いることが有効です。例えば、平均値、標準偏差、相関係数などを算出することで、データの傾向や特徴を客観的に把握することができます。また、グラフや図表を作成することで、データを視覚的に分かりやすく表現することができます。
他のフレームワークとの連携
3C分析の結果は、SWOT分析、STP分析、4P分析など、他のフレームワークと組み合わせて活用することで、より効果的なマーケティング戦略を立案することができます。
SWOT分析は、3C分析の結果を整理し、戦略を具体化する上で役立ちます。STP分析は、3C分析で得られた顧客情報を基に、ターゲット顧客を明確にする上で役立ちます。4P分析は、3C分析とSTP分析の結果を基に、具体的なマーケティング施策を検討する上で役立ちます。
例えば、3C分析で市場の機会を発見し、SWOT分析で自社の強みを活かせることを確認したら、STP分析でターゲット顧客を絞り込み、4P分析でターゲット顧客に合わせたマーケティングミックスを構築することができます。このように、複数のフレームワークを組み合わせることで、より整合性のとれた、効果的なマーケティング戦略を立案することができます。
3C分析の応用:4C分析、6C分析との違い
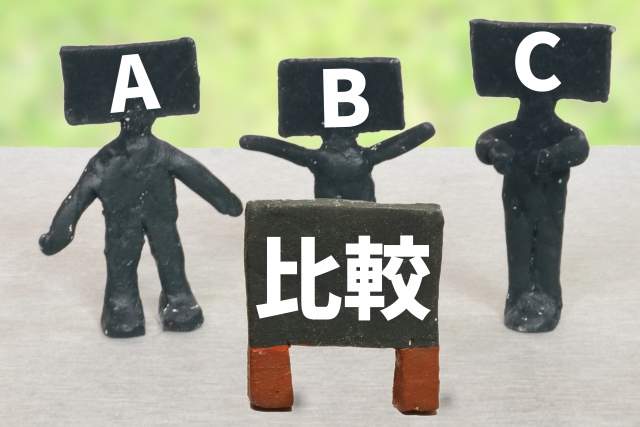
4C分析とは
4C分析は、CustomerValue(顧客価値)、Cost(コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)の4つの視点から分析を行うフレームワークです。3C分析を顧客視点からさらに深掘りする際に有効です。
顧客価値は、顧客が製品やサービスから得られる価値を指します。コストは、顧客が製品やサービスを購入するために支払う費用を指します。利便性は、顧客が製品やサービスを入手したり、利用したりする際の容易さを指します。コミュニケーションは、企業と顧客との間の情報伝達を指します。
4C分析は、顧客視点に特化しているため、顧客満足度を高めるための戦略を立案する上で役立ちます。例えば、顧客価値を高めるためには、製品の品質を向上させたり、新しい機能を追加したりすることが考えられます。コストを下げるためには、生産コストを削減したり、流通経路を効率化したりすることが考えられます。利便性を高めるためには、オンライン販売を導入したり、店舗の営業時間を延長したりすることが考えられます。コミュニケーションを強化するためには、SNSを活用したり、顧客サポート体制を充実させたりすることが考えられます。
6C分析とは
6C分析は、Control(統制)、Circumstance(状況)、Competitor(競合)、Customer(顧客)、Company(自社)、Consortium(協力者)の6つの視点から分析を行うフレームワークです。より複雑な市場環境を分析する際に有効です。
統制は、政府の規制や業界の自主規制など、企業を取り巻く規制環境を指します。状況は、経済状況や社会情勢など、企業を取り巻く外部環境を指します。協力者は、サプライヤー、販売代理店、提携企業など、企業と協力関係にある組織を指します。
6C分析は、3C分析に加えて、規制環境、外部環境、協力者との関係性をより考慮するため、より包括的な分析を行うことができます。例えば、新興国に進出する際には、その国の規制環境や社会情勢を考慮する必要があります。また、サプライチェーンを構築する際には、サプライヤーとの良好な関係を築く必要があります。
まとめ:3C分析で競争優位性を確立しよう
3C分析は、マーケティング戦略を成功に導くための強力なツールです。本記事で解説した手順とポイントを参考に、ぜひ3C分析を実践し、自社の競争優位性を確立してください。
3C分析は、一度行ったら終わりではありません。市場環境は常に変化するため、定期的に3C分析を実施し、戦略を修正していく必要があります。また、3C分析の結果は、企業全体の戦略だけでなく、個々の部門やプロジェクトの戦略立案にも活用できます。
競争優位性を確立するためには、3C分析の結果を基に、自社の強みを最大限に活かし、弱みを克服するための戦略を立案する必要があります。また、常に顧客視点を忘れず、顧客ニーズに合った製品やサービスを提供することが重要です。
うるぷろでは、本記事で紹介した3C分析などのフレームワークを活用しながら戦略を導き出すプロのコンサルタントを多くパートナーとしています。事業戦略の策定にお困りの事業者さまは、是非一度弊社にお問合せください。



